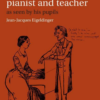ラフマニノフ 底なしの悲嘆と絶望
十数年前、のだめカンタービレと言うドラマで玉木宏さん演じるチアキ君がラフマニノフのピアノ協奏曲第二番を演奏した回があったのですがそれが初めてラフマニノフという作曲家を知るきっかけとなりました。

第二協奏曲は美しい短調的な旋律で書かれ、第一楽章から第三楽章は悲しみを乗り越えて克服や勝利にたどり着いたことを意味するように表現されているように思います。
ラフマニノフの旋律に魅了され、ある時ずっとその協奏曲のCDを買って聴いてました。
ただ、本格的ラフマニノフのピアノ曲を弾き始めたのはそれから5−6年後のことでした。
彼の前奏曲を弾くと、そこには彼の有名な曲のような悲しくて美しいラフマニノフと言う印象ではなかった。
若き頃のラフマニノフの印象は全く違う別のラフマニノフがいました。
ラフマニノフは手短に言えば:底なしの悲嘆と絶望。
悲痛、嘆息、絶望、おそらく死に向かう何かを感じます。
今考えてみると当時のだめカンタービレの演奏のテンポはやや遅く、どちらかというとロマンチックな演奏でした。
しかし別の演奏家のラフマニノフ第二を聴くと、ロマンチックなど一粒もない世界だった。
特にラフマニノフ自身が演奏されたレコーディングでは、第一楽章の和音序奏と後に続くアルペジオは激しい感情の揺れ、疾走、絶望の叫びでした。
単なる悲しみではない咆哮。
ロマンスなど、微塵もない。
実際ラフマニノフという作曲家はかなり神経質だったそうで、情緒の乱れも激しく、この第二協奏曲を作曲する前にうつ病になっていたみたいです。
その第二協奏曲に作曲中に心理治療を受けてラフマニノフはこのとてつもない傑作を世に送り出しました。
時々この曲を聴きたくなる時があります。特に自分がうつになった頃はよくお世話になっています。ラフマニノフの作品集でも現在の自分の置かれている環境やその虚しさや希望のなさを曲を聴きながら味わい、楽しんでいます。(笑)
ラフマニノフは一体どうやってその希望も無く沈んでいく感情を音楽で表現したであろうか、ちょっとだけ考えて分かち合いたいと思います:
作曲された曲はほとんど短調です
これほど短調を使った作曲家がいるのかと思うぐらい、ラフマニノフは短調を愛用しています。
例えば、エチュード集Op. 39の場合、長調は9曲の中1曲だけしか含まれていません。
作曲されたエチュード、前奏曲集や交響曲一部の楽章は長調に書かれていますが、それでもモーツァルトやメンデルスゾーンみたいな明るい楽しい表現を一切持たず、何かに対しての思慕やノスタルジアなど連想させます。
そのため、作曲された曲集は全体的に暗く、いくら長調を書いたと言え、虚しさと憂鬱と切り離すことはないのです。
和音を多用している
ラフマニノフの特徴の一つといえば、和音を多用していることだと思います。
彼のピアノ協奏曲はもちろん、プレリュードやエチュードやピアノソナタも和音だらけです。
もっともラフマニノフ自身がコンサートでもっとも弾いたプレリュードOp. 3-2はその和音の響きが特徴的です。
それにラフマニノフがよく使われている和音の一つは増三和音(Augmented triad)なのです。
このコードは音楽和声上非常に不安定で、聴いてて不気味で不吉な気持ちにされます。
これはラフマニノフにとっては曲作りの絶好の材料であり、よく作品に取り入れられています。
今、僕が練習しているラフマニノフのエチュードOp. 33-9もそうです。

その和音も多さはなぜかというと、次のポイントにつながります。
鐘の響き
ラフマニノフは鐘の響きを表現する箇所が多いです。
少年時代のラフマニノフはロシアで鐘の音を耳にした影響かもしれません。
おそらくもっとも有名なのは先ほども語ったOp. 3-2の前奏曲、別名「鐘」です。
AーGシャープーCシャープの流れでその鐘の響きを表現されてます。

展開部もその重いCシャープオクターブが特徴的です。

その重い和音で曲の全体を支え、響きが満ちた中で悲しげな旋律が奏でられる。
まるで最後の審判のような風景を思い出させるような感じです…
それについてですが、実はラフマニノフは最後の審判と関連したものをさまざまの作品で示しています。
Dies Irae (怒りの日)テーマ
Dies Irae(ディーエスイレ)はラテン語で「怒りの日」。中世欧州で教会や修道院でよく歌われている讃美歌(グレゴリオ聖歌)の一つです。
レクイエム(死者のためのミサ)などのミサ曲でもよく使われています。
モーツァルト・ベルディなどレクイエムに独自のディーエスイレを作曲しました。特にベルディのはおそらくテレビやゲームのBGMなどよく使われています:
ベルディレクイエム動画(こわいていうか、コメディで出てきそうで笑ってしまうぐらいのインパクトです。)
本来の旋律は以下のビデオのように:
当時は長調短調を使わず、ドリア旋法が使われたようです。
ドリア旋法について(Wikipediaから):https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%97%8B%E6%B3%95
ラフマニノフはこのディーエスイレの旋律を自分の作品に取り入れています。
彼が正教会を信仰してた影響かもしれませんね。
こちらの動画はエチュードOp. 39-2:
聴いてて一目瞭然だと思いますが、最初からすでにディーエスイレのメロディーなのです。(出だしの四分音符:CーBーCーA)
パガニーニの主題による狂詩曲でもところどころにディーエスイレのテーマが現れます。
やはり死に対して何か感じたのではないでしょうか… ラフマニノフ
簡単にラフマニノフの曲を作り上げた要素をちょっとまとめました。まだいろんなありますが、今日はここまでにします。
ところで、ラフマニノフの曲を弾くときもレガートを注意しています。レガートについて:https://lifejpn.clavierloner.com/?p=76
ではまた!