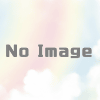レガートの重要性とその魅力: 日々の練習とカラヤンの教えレガート
最近、ショパンのエチュードをの教授のもとでZoomを通じて勉強し直しています。教授はよく「ノノノノノー、レガート!レガート!」(“No no no no no, Legato! LEGATO!”)を繰り返して言います。

革命エチュードの挑戦
この箇所はこの一ヶ月よく練習するところなんですが、革命エチュードの最初の左手の部分は思ったより難しいです。特に一つのフレーズを流れて歌うようにペダルなしに弾くのは結構時間がかかりました。
滑らかに弾くため、一箇所の練習は一回で1〜2時間の練習が必要な場合もあります。そのレガートのため毎日練習して悩まされています(笑)。今はなんとなくレガートに弾けるようになり、教授からゴーサインが出て、ついに新しい課題をいただきました!
「やっっっっっタァぁぁぁぁ!」
それで、この数日、ベートーベンの悲愴やラフマニノフの練習曲など練習し始めてます。
レガートとは何か?
レガートは音と音の間に切れを感じさせないよう滑らかに弾くという意味ですが、実際はそう簡単にはできません。ピアノは弦楽器と違って一つの打鍵で一つの音やコードしか出せないため、弦楽器のように連続して音を出すことが難しいのです。
ピアノのレガートは音と音の間に隙間なく素早く弾くことだと思われがちですが、それだと、二つの音がガチガチにブツ切れにされているようにしか聴こえないのです。教授が教えるレガートは、音の響きを一つ一つ聴いて、音と音の間が繋がっているように弾くことです。
教授が毎回スラスラとお手本を見せしてくれます。Zoomなのに教授のレガートは魔法のようで、美しすぎていつもその技術に感動しながら聞いています。音のつながりを聴いて感じて、それを音ではなく音楽に変えることが毎日の課題です。
カラヤンとレガートの美学
先週ちょっと疲れてYouTubeでランダムに色々なオーケストラのベートーベン第九を聴いていました。確かに音色とオーケストラや合唱団のバランスは素晴らしいのですが、ちょっと物足りないなぁと感じていた時、その動画の隣にあるお勧めリストに載っていたカラヤンの指揮した録音ビデオが目に入りました。
カラヤンの魔法
やはりカラヤンだよな…。昔からカラヤンの指揮が好きで、彼のベートーベン第七交響曲やブラームス第四交響曲は今もお気に入りです。
カラヤンは「帝王」とも呼ばれた人物で、幅広い音色、レパートリー、力強いけど滑らかな指揮で世界を魅了した指揮者です。彼はよくオーケストラの独裁者とも言われてました。自分をかっこよく見せるため指揮台をわざわざ高くしたり、映像を録画するとき顔の左側から撮るように要求したり、当時では相当触れてはならないと思われている録音音声を調整したり、ナルシストで色々とオーケストラのメンバーに嫌われたそうですが、それでも彼のインパクトが凄まじく、その音楽は感動を与えてくれます。
第一楽章だけ聴いてみると、本当にフレーズが長く膨張していくように聴こえます。その悲愴さや重みはレガートでバイオリンの旋律やチェロのベースラインに沿って拡大していくように聴こえます。
カラヤンの別名は「レガートの帝王」だそうです。音楽は常に流れることを意識し彼はいつもそれをオーケストラに要求してます。昔残されたリハーサル映像にも確認できます。
「小節線は音楽の呪いだ。」
彼は小節線をあるマスタークラスでこう述べていました。それはただの楽譜に変えている参考にすぎないのに、そのせいで人々はそのフレーズを切り離してしまう、というのがカラヤンの考えだそうです。
彼のベルリンフィルの録音を聴いてみると、弦楽のボーイングを変えている雑音も全く聴こえず、フレーズをスムーズに運んでいます。全てのフレーズがつながり、音楽の一体になっていると感じます。
レガートを極める日々
余談ですが、前回教授とのレッスンの時にカラヤンについてどう思われたのかと聞くと、教授もカラヤンが好きで、彼のその音楽細部への留意やこだわりに感心していると仰っていました。
どの楽器でもレガートは音楽の感動に欠かせないものみたいですね…。これからもレガートをマスターして、もっといい音楽を奏でたいと思います!
ではまた!