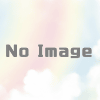休日 ベートーベン悲愴第一楽章
今日は休日です!普段朝、起床時間ははやいのですが、今日は1時間遅く起きれてよかったです。(遅いと言っても6時ですが)。今朝はベートーベンの悲愴、ショパンやラフマニノフの練習曲など練習して過ごしてました。

練習後に飲んで気持ちもリフレッシュ!
さて、ベートーヴェンの悲愴についてですが、この曲は自分がピアノ始めてから半年ぐらいに挑戦した曲として思い出深いです。
もちろん、挑戦は見事に失敗しました。
「ピアノ習い始めてから半年でこの大曲弾けるとでも思ったか??」
当時の自分はやっぱりベートーベン好きすぎて、基礎もちゃんとできてないのに無理難題を突っ走り苦しい独学の時間を過ごしました。
これが若さか…

今は割とスラスラと弾けるのですが、やっぱり音楽面や技術面でも相当難しい部分があって、今日はそれを3つほど語りたいと思います。
1)最初のページ・グラーヴェについて
悲愴第一楽章の出だしはグラーヴェ (イタリア語:Grave、重々しく)。出だしのフォルテピアノ(fp, fortepiano)や付点リズムが特徴で、表現と安定したリズムが要求されます。

その重苦しいコードの序奏は悲愴らしい始め方ですね。
ただ、悲愴と思いきや、最初はフォルテピアノだけです。フォルティシモやfffでもありません。
当時のピアノも構造はあんまり強くなく、ベートーベンがピアノを弾く時しょっちゅうピアノを壊してしまう場面は様々な記録に残されてます。
時代が進むと、ピアノも進化して、ロマン派のチャイコフスキーやラフマニノフのように強烈な音響も表現できるようになり、fffやffffをもっと記譜するようになりました。
もう一つの点は、展示部のあとの間奏にその序奏のテーマがまた現れます。この時もfpと表記されてます。
ベートーベンはなにを表現したかったのでしょうか。

難聴に悩まされ、徐々に聴覚を失う日々。
耳は音楽家にとってもちろん極めて重要なので、それを失うということは作曲家のベートーベンにとっては命取りでしょう…
ベートーベンはその悲愴の序奏でそのどうにもならない絶望を表現したかったのでしょう。元々ウィーンで期待されてた若手の音楽家が、まさか耳が聴こえなくなるとは。
今まで努力した意味はなんだったのか… その才能を奪われるのか…
手を高くしてピアノに思いっきりガン!っと弾くのではなく、鍵盤の底から重みを置いて引っ張り出すように弾く?
悲しみ尚且つ憂鬱な響きを出すのはないでしょうか。
その重苦しいコードから続く弱奏(ピアノ、piano)で弾く付点のリズムですが、ベートーヴェンの自分の運命に対する嘆息でもあるかのように感じます。。
この付点リズムをちゃんと遅いテンポに合わせてリズム通りに弾くと、ベートーベンの心の底に嗚咽しているようにも聴こえます。
ここでルバート(テンポを自由に)で表現する方もいらっしゃいますが、自分は譜面通りに安定したテンポとリズムを好みます。
ベートーヴェンの初期の作品の一つなので、安定したテンポで弾くのはおそらく当時の慣例だと思われます。
フォルテとピアノの繰り返し、おそらくベートーベンは自分の人生に対する激怒、絶望、憂鬱を表したかったのではないでしょうか。
2)展示部:左手のオクターブトレモロと伴う疾走感
おそらくこの左手のオクターブトレモロをマスターすることはこのソナタで一番の課題の一つでしょう。このトレモロを素早くかつリラックスして弾くのは非常に難しく、時間をかけて研究して練習する必要があります。

その左手のテクニックですが、一言で言うと親指、小指、手首を完全にリラックスして、この二つの指の関節を全部使って鍵盤のそこから引っ張り上げる感じです。指を引っ張り上げる際、手首をその動きに順ってちょっとあげます。
指を引っ張るというか、ねごが鍵盤に戯れる感じです。
必ず手首を固定しないことを念頭におきましょう。
そうでないと、手を痛めたり、最悪の場合…手を壊します。
3)やはり、響のレガート
約15年後にこの曲と再会して、今だからこそ思うのはこの曲のアジタート(イタリア語:agitato、激しく)的な感動を与えるには響のレガートが不可欠だと言う事です。
この悲愴の原典版を読んでると、ベートーベンはあんまりスラーを書いてないです。
だからと言って、このソナタの全体に渉る右手のスタッカートをスタッカートのままで弾くと、全部ぶつ切れにしか聴こえず、その曲がもっとも重要である疾走感を失ってしまいます。
そのため、スタッカットを弾くとき音の尻尾、すなわち響を聴きそのラインに沿って繋げていく必要があります。
音を一つ一つを聴いて歌い、自然に小さなクレッシェンド(次第に強く)やディミヌエンド(次第に弱く)ができて、フレーズがてきます。
その効果を出すには結構時間かかると思いますが、ゆっくり練習することがこの点について非常に重要です。
音を一つ一つを感じて弾き、その響を繋げていく作業を繰り返していきます。
今も毎日展示部の左手のトレモロや右手のスタッカートのラインに集中して練習しています。頑張ります(^^;)
レガートに関する記事はこちらへ:レガート