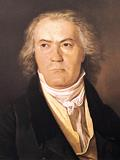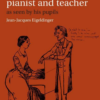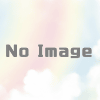レッスン苦闘 5・15
なぜか今回の教授は静かだった。
昨日弾いた曲は前回も弾いたショパンのエチュードとベートーベンの悲愴、加えてラフマニノフのエチュードと一部のスカルラッティのソナタ。
ショパンのエチュードはまだ左手慣れてないのでまだちゃんと弱音で弾けてないのですが、教授は今のところはちょっとテンポを落として練習して、慣れたらフルテンポでいきましょう、っとアトバイスしてくださいました。
それだけでした。教授はなぜが反応が薄く、自分のパフォーマンスはいいのか悪いのか、教授の顔では見当がつかない。

レッスンでちょっと閃いたのは、その左手伴奏を弾く際、最初に掌全体を鍵盤に近づけて、長い指を意識しながら指先だけで鍵盤を撫でいくようにと考えるようになりました。手首もその動きに沿って回します。
あと余計なテンションを感じることは何かが間違っている印だということです。
その次に、ラフマニノフのエチュードOp. 33-8。
ベートーベン悲愴と同じく、テンポはグラーヴェと書かれています。しかし蓋を開けると16分音符の6連符のバスやところところに32分音符があります。

おそらく、ラフマニノフがグラーヴェを買った理由はそのテンポより曲全体の重さの雰囲気を強調したかったのでしょうか。
教授はラフマニノフの曲をシンフォニックに(交響曲的に)考えるようアドバイス。すなわち、このエチュードは縦から見るとパートがいくつあるからです。
このパートたちを自分である楽器を想像して弾いてごらん、と言われました。

青:トロンボーンなど
赤:弦楽器など
それに加え、横でパートとパートの間に時間と空間を与えること。

様々なパートたちがもたらす音の尻尾を聴いて合奏するように、と。
それもそれだげで「OK、次は何を弾く。」と聞かれました。
なんかもっとラフマニノフに集中して指導受けるかと思いましたが…
その次は、ベートーベン悲愴。第一楽章と第三楽章へ…
全体的には弱音のところを本当にピアノpianoで弾くようにとのこと。
例えば:

しかし弱音だからといって、手首を硬くしたり、芯がない音はだめです。
弱音は難しい…
ところどころで楽譜の解釈をいただき、悲愴は終わりました。
最後の数分だけ、スカルラッティのソナタD. 141の単音トレモロを弾きました。
それも特にアドバイスはなかったのですが、そのトレモロを弾くときも指を鍵盤で走らせながら、手首はその指の動きに沿って回すように動くと…
教授はよく手首を「羽のように」と仰ります。手首の動きは早く弾くには欠かせない重要な役割を果たしてくれるようです。
でも、今回のレッスンはなぜか教授の反応が薄く、心配です。
むしろ、前回のレッスンで感情剥き出しでムッとして指導されてる教授の方がずっと安心するようにも感じます。 苦笑
最後のコメントも「いいね。次はバッハでも加えましょうか。それにベートーベンの暗譜を始めましょう。では二週間後に会いましょう。」と淡々と仰って授業は終了。
自分はベートーベンのソナタは殆どを弾いたことがあり、暗譜も苦と思わないのでいいのですが、音一つ一つちゃんと意味を持って表現しているかといつも練習中に神経質になり、授業中にもすらすら弾けないことがあります。
でもやっぱり、ゆっくり練習して一つ一つ音を確かめるしかない。あと、深く考えすぎない。矛盾しているようですが、やっぱり、バランスじゃないか。😅
以上、今回のレッスンでした。