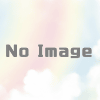クラシック音楽という過酷な世界:ピアニストの夢と現実
クラシック音楽という過酷な世界
通勤時に海を見ることがよくあり、考え込むことが多いです。これからの仕事、人生の目標、親を養うことや将来の家庭を築くことなど、色々悩んだり、今の自分を分析したり、考え直したり。
最近海を見てよく思うのは、自分はいかにこの世の中で小さい存在かということです。特にクラシック音楽の世界に飛び込むこと自体、他の人から見ると愚かの極まりかもしれません。
クラシック音楽界は言うまでもなく競争は激しく、弱肉強食な世界と言っても過言ではないです。海を見てるとこのクラシック音楽界を見ているような感じもします。境界なき大洋と比べると自分はいかに小さな存在かと。
その世界は才能と才能とのぶつかり合いの地獄で、無数の英才教育を受けた人や天才だけが立つことを許される土俵です。毎日楽譜と音との戦いで、練習漬けも日常茶飯で、その音一つ一つの細部までこだわって追求しなければいけません。
よくYoutubeでも見かけますが、英語で検索するとよく「7歳がショパンのエチュードを弾く」など年齢の若さや曲の難しさをアピールするタイトルの動画がたくさんあります。今も常に「最年少」コンクール受賞者やそういう若く開花した才能たちを祝うニュースやSMSが世の中に流れているのでしょう。
若い子供たちが難曲をスラスラ弾けるのはやはり小学5年生でピアノ始めた自分にしたら魅力的な部分もありますし、その子供たちを見ていると、やはりこのクラシック音楽界の厳しさを毎回思い知らされます。
日々のレッスンと音楽の道
毎回教授とのレッスンをするときも、教授はお手本を見せてくださるのですが、その美しい響きとフレーズに心を奪われます。その上、前回の授業に教授は筆者と次の演奏プログラムや課題を考えされるときも、ピアノでスラスラとしかも暗譜で10曲以上の提案を即座に、一つ一つ曲の初めの部分を弾かれました。(何者なんだこの方…)
自分は中山七里さんの岬洋介シリーズを愛読しています。最新作のおわかれはモーツァルトはまだ未購入ですが… (まだ新しいのでちょっと値段が高く買いづらいです…)
中山さんはその音楽とミステリーを融合して小説を書いてらっしゃって、斬新で音楽の細部への描き方には感心します。
その作者の小説を読んでますと、クラシックピアニストの世界はやはりいかに生きづらいかと考えせざる終えません。よく小説にも書かれてありますが、「音楽の神」に祝された人だけが生き残れる世界のようなものです。数年前も蜜蜂と遠雷という映画も上映されました。自分は小説版しか読んでいませんが、やはりその小説でも生々しくピアノ界のトップに君臨するのも努力し尽くしている秀才たちと神童たちです。
音楽の追求と自分の道
世の中にコンサートピアニストを目指している人も無数にいるにもかかわらず、その頂点まで辿り着くのはほんの一握りだけです。では、なぜ自分は音楽という道を選んだのか。なぜこれほど過酷な世界に飛び込もうとするのか。
それを自分に問いかけてみると、やはり答えは一つしかありません。
音楽の美しさと感動を味わうために追求し尽くしたい。その芸術を極めるために修行し続け、人生を全うしたい。音楽界で有名や商業的に成功しているピアニストになるよりは、音楽の真髄を探求し、辿り着き、自分や人々を感動させたいというのが願いです。
今、社会人として働いていながらも練習や勉強漬けの毎日ですが、それでも音楽を追求したいという気持ちが絶えず膨らんでいきます。
これほど夢に対する執着を考えてみると、音楽は恵みなのか、呪いなのか…